1.5 知的所有権
1.5.1 インターネットと知的所有権
インターネット上の文章・記事・音楽・絵画・写真などの情報は,デジタル化された情報である.以前は,印刷物,電話,ラジオ,テレビを媒介手段として流通する情報は,すべてアナログ情報であった.アナログ情報の場合,情報の編集,加工,コピー,配布などの作業に手間と時間がかかり,容易ではない.それに比べ,デジタル情報の場合,コンピュータなどの情報機器を用いることによって,情報の編集,加工,コピーの作成などを,容易に行うことができる.さらに,インターネットを利用すれば,情報の配布も容易にできるようになってきた.
私たちにとっては,次に示す二つの機会の増加によって,知的所有権に対しての理解が大切になってくる.
一つは,デジタル情報を取り扱う機会が増加し,他者の知的所有権に対して気を配る必要が出てきたことである.デジタル化された情報は,編集,加工,複製,保存,配布が,容易に,大量に,確実に行われるため,書物,絵画,写真,映画などの創作物は,過去の創作物をも含めてデジタル化されている.デジタル化された創作物は大量に複製され,CD-ROMなどの情報の記録媒体として商品化されている.また,インターネットを通じて,入手することも可能である.さらに,さまざまな情報機器を使って,個人的にアナログ情報をデジタル化することも可能になってきた.私たちは,これまでに比べて,デジタル化された他者の創作物を取り扱う機会が増えてきた.デジタル化された創作物は,コンピュータによって容易に加工したり,コピーしたりすることが可能である.知識が無いために,ついうっかり他人の創作物を配布するなど,著作権を侵害し,加害者になってしまうことが充分考えられる.したがって,創作物に対して与えられている知的所有権に関して理解していく必要が高まってきた.
もう一つは,インターネットによる情報発信の機会の増加に伴う,自己の創造物に対する知的所有権の理解である.今日まで,私たちは,どんなに優れた著作物を創作したとしても,その著作物を他者に伝える手段を持っていなかった.しかし,インターネットの普及により,個人での情報の発信が大変に簡単になった.これまで,新聞社や放送局などのマスコミにしかできなかった情報の発信を,インターネットを利用することで,われわれ個人でも行うことができるようになった.例えば,Webページに公開した自分の創作物は,世界中の人々が閲覧することでき,必要ならその情報を容易に取り込むことができる.こうして,製作者の意図に関わらず,個人の創造物が,無断で複製され,売買される危険性が高まってきている.したがって,自己の創造物に対して発生する著作権について理解することが,重要になってきた.
このように,デジタル化とインターネットの発展によって,一部の専門の事業者だけでなく,私たちも日常生活の中で著作権に代表される知的所有権にかかわる機会が増えてきている.デジタル化された情報は,オリジナルと全く同一の情報を,短時間に,しかも大量に複製することが可能である.音楽,ビデオ,ゲーム,ソフトウェアなどの著作物の違法コピーが,技術的に誰でも容易に行えるようになり,著作者が苦労して創り出した著作物と同一の複製品が,いとも容易に作り出すことができる時代を迎え,著作権は著作者を守る権利として重要性を増している.
一方,米国では,著作権の精神を尊重した上で,非営利目的の授業,研究,調査などを行う場合に,著作権の適用を除外する「フェアユース(fair use)」の概念が登場している.フェアユースの例として,著作物を利用する著作利用権の考え方を用いて,一定の料金を支払った上で利用することができるシェアウェアもある.さらに,PDS(Public Domain Software)として,公共での利用をむしろ推進するために,著作者自身の意志によって,著作権を主張せずに自由にコピーや改変を認めているものもある.いずれにしても,著作権者の意向を尊重して著作物に相対する精神を忘れてはならない.図1.2は,知的所有権の全体的な構成を示している.
1.5.2以降に,著作権,著作者人格権,著作隣接権,工業所有権など,知的所有権の中で私たちが理解する必要のある内容を解説する.
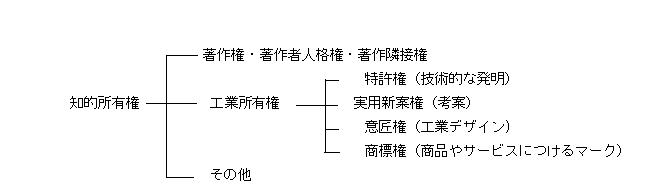
図1.2 知的所有権の構成図
1.5.2 著作権
著作権法は,著作権,著作者人格権,著作隣接権によって構成されており,著作者等の権利を保障し,文化的所産の公正な利用を図り,文化の発展に寄与する目的で制定されている.その中で,著作権は,著作物の利用に関して著作者が有する権利の集合体であり,複製権,上演・演奏権,公衆送信権,口述権,展示権,上映・頒布権,貸与権,翻訳・翻案権,二次著作物利用権などから構成されている.著作者はこのような権利を行使することによって,次のように,創作活動の対価としての報酬を得ることができるようになる.
例えば,音楽の作曲や作詞を手がけているような著作者は,自分で作曲あるいは作詞した音楽で利益を得るためには,その音楽を演奏してCDなどを制作し,公衆に宣伝して販売しなければならない.しかし,実際には,著作者自らが演奏して,CDを制作・販売することは難しい.そこで,著作者は所有する著作権を行使して,歌手や演奏家,レコード製作者,放送事業者などに対して演奏,複製,放送等を許諾し,その使用料を得ることができる.
また,著作物とは,著作者の創意工夫によって創り出される創作物であり,文章,音楽,舞踏,美術,建築,地図・図形,映画,写真,プログラム,二次的著作物,編集著作物,データベースなど,多岐にわたっている.表1.2に著作物の種類と具体的な例をまとめている.
表1.2のような著作物に対して,著作権は設けられている.日本の場合,無方式主義が取られており,著作物が創作されると,自動的にその著作物に対して著作権が設定される.一方,著作権は,その著作物を保護する期間が決められており,著作者の死後50年である.また,私的利用のための複製,図書館等における複製,引用,教育目的のための使用,営利を目的としない上演,政治上の演説等の利用,プログラムのバックアップ用の複製などは可能であり,著作権法上の制限を受けない.
しかし,MDやDVDのようなデジタル方式の録音,録画媒体の普及に対応するため,1992年著作権法が改正され,著作物のデジタル方式での録音・録画を行う場合には,たとえ私的な使用にとどめる場合でも補償金を支払うことになった.なお,憲法や法律,国や地方公共団体の告示,通達,裁判所の判例など,公共性を有する公文書は,著作権を有する著作物ではない.また,事実のみを伝える報道も著作権を持たない.
|
<デジタル録音> 音楽用の録音用MD(MiniDisk)は,CDからデジタル録音することができる.しかし,このように録音されたMDから他のMDに,再びデジタル信号のまま録音することは,著作権などの配慮からできないようになっている.すなわち,「コピーのコピー」をつくることはできないようになっており,このことを SCMS(Serial Copy Management System)と呼んでいる. <音楽著作権とMP3> MP3(MPEG Audio Layer3)は,音声データの圧縮技術で,MP3を利用すれば標準音声を10分の1程度に圧縮できる. インターネット上の音楽ファイルは,そのままではファイルが大きいので現実的には利用しにくい.そのために,あまり音質を落とさずに音声を圧縮できるMP3が利用されてきている.しかし一方では,MP3で音楽ファイルを圧縮して,無許可で配布する違法なWebページが増えてきており,悪質なケースは検挙されている. |
著作物の種類 具 体 例 デジタル情報との関連 言 語 小説,脚本,論文,詩歌などの他に,創作性のある書簡なども含む. E-Mail,電子掲示板,Webページなど,インターネット上で公開,あるいはインターネットを経由する文書は著作物.
(ただし,事務連絡など,創作性の無い掲示やメールの文書は著作物ではない) 音 楽 作曲,作詞 デジタル化された創作性のある音楽(歌謡,サウンド,旋律など)は著作物. 舞 踏 舞台での演技者の振付け CG(Computer Graphics)や3D作成ソフトで制作した振り付けは著作物. 美 術 絵画,彫刻,版画,漫画,書,挿し絵 CG(アニメーションも含む)は著作物.Webページのデザインや動画は,著作物である. 建 築 建築物自体(建物の写真は著作物ではない) 建物の写真は,建物の著作者の許諾なしにWebページに載せてもよい. 地図・図形 地図,学術的な図表,模型,設計図 Webページ上に公開されている地図,図・表,イメージマップは著作物. 映 画 上映用映画,テレビ番組,ビデオ作品,ストーリー性のあるコンピュータソフト Webページ上のストーリー性のあるデジタル映像,ストリーミング配信映像・ライブ 写 真 創作性のある写真,グラビア,ポスター写真 創作性のあるデジタル写真,電送写真.Webページに載せる写真も著作物 プログラム コンピュータ・プログラム ソースおよびオブジェクトプログラムは著作物.ただし,プログラム言語自体,プロトコルやインターフェースの規格は著作物ではない. 二次的著作物
著作物の翻訳,編曲,彫刻を絵画にするなどの変形,脚色,映画化,現代語訳やダイジェストを作成するなどの翻案 コンピュータで文章,画像,映像など他者の著作物を取り込み,一部を改変,あるいは統合した創作物は二次的著作物.ただし,素材にした著作物の利用に関しては,原著作者からの許可が必要. 編集著作物 百科事典,辞書,詩集,判例集,新聞,雑誌など.素材の選択や配列などに創造性を有するもの. デジタル化された百科事典,辞書,雑誌のバックナンバーなどは編集著作物. データベース
論文,数値,図形などのデータベースで,検索が可能なもの. 効率よく検索できるように,工夫して素材を配列,保存したデータベース.検索で得たデータが著作物の場合は,著作者の許可が必要.
次に,インターネットの利用において,特に関係すると考えられる著作権について解説する.
a)複製権
複製権とは,印刷,写真,コピー,録音,録画などを行って,原著作物の複製物を作る権利である.この権利は,著作者が独占的に所有している.出版社,レコード会社などは,著作者に複製の許可を受けて,大量に印刷・コピーして販売する.一方,著作者は,複製の許可を与えたことによって,著作物の使用料や印税などの対価を得る.
前述のように,著作物のデジタル化とネットワーク化が進み,コンピュータで容易に著作物を複製することができるようになってきた. CD-ROMなどのデジタル記録媒体やインターネットを通じて,文章,デザイン,画像,音声,映像,ソフトウェアなどをコピーする行為はこの複製にあたり,著作者の許諾なしに複製を行うと,複製権の侵害にあたるので注意が必要である.
b)公衆送信権
公衆送信権は,テレビ,ラジオ,CATVなどを利用して著作物を一斉送信する,あるいは,インターネットなどの通信媒体を通じて利用者の要求に応じて著作物を送信する権利である.従来,この権利は放送権・有線放送権と称され,テレビやラジオなどの同内容の一斉送信のみの配信に対応していた.しかし,送受信技術の進歩と情報インフラの整備により,WWW,CSなどのデジタル放送,また将来実現されるであろうビデオ・オン・デマンド(Video on Demand)など,インタラクティブな著作物の送受信に対応するように法律の改正が求められてきた.このような著作物の新しい配信方法に対応するために,1997年に著作権法が改正され,この公衆送信権が1998年から施行されている.したがって,公衆に情報を発信するために,プロバイダのWebページに著作物のファイルを送信して著作物を公開することが,著作者の権利として著作権法で保障されることになった.
c)二次的著作物の利用権
デジタルコンテンツは,コンピュータ上で複製が容易であると同時に,原著作物の編集,改変,統合などが容易である.したがって,CD-ROMやインターネットを通じて入手した文章,図画,写真,音楽,映像,プログラムなどの著作物を,簡単に変形し,改作することが可能である.このように他者の著作物を改変する場合は,事前に原著作者に対する許諾が必要である.また,改作した著作物は二次的著作物になるが,原著作者の権利が消滅する訳ではなく,原著作者は,二次的著作物の著作者の権利と同等の権利を有する.
1.5.3 著作者人格権
著作者人格権は,公表権,氏名表示権,同一性保持権から構成され,著作者の人格を尊重し,保護する目的で制定されている.公表権は,自分の未発表の著作物を公表するか,否かを決定する権利である.氏名表示権は,著作者の実名,あるいはペンネームを明示するか否かを決定する権利である.また,同一性保持権は,著作物の内容や題名を,著作者の意に反して改変させない権利である.デジタル時代を迎えて,特に著作物の改変が容易に行われるようになり,この原著作物との同一性保持の問題に関しては,著作権のみならず,著作者人格権の侵害にもつながるため,特に注意を払う必要が増してきた.
イラスト・写真・キャラクタの一部を改ざんして違う作品にしてしまう行為は,著作権と著作者人格権の侵害に当たる.写真やイラストをデジタル化して,一部に手を加えてWebページに掲載する際には,著作権と著作者人格権の侵害に注意する必要がある.
1.5.4 著作隣接権
著作隣接権は,演奏家,歌手,俳優などの実演家,レコード製作者,放送事業者や有線放送事業者に与えられた,著作権に準じた権利である.すなわち,実演家,レコード製作者,放送事業者に対して,録音・録画権,レコード複製権,放送権などを与えて,実演家の演技や演奏,レコードやCD,放送内容を保護するものである.
実演家の権利として,自分の演奏や演技を,録音・録画し,貸与し,あるいは放送する権利を有している.したがって,例えば,歌手が自分の歌を録音してレコードにしたり,放送で流したりする場合,許諾を与えて報酬を得ることができる.実演家のレコードやビデオを放送事業者が放送する場合,放送事業者が実演家に対して支払う報酬を,二次使用料という.同様に,レコード製作者もレコードの録音・録画,貸与,放送を独占する権利を持っており,製作したレコードを再生して録音・録画する場合やレンタル会社に貸与する場合,あるいは公衆に放送する場合には,許諾を与えて報酬を得ることができる.さらに,放送事業者や有線放送事業者は,放送の複製権や再放送権を持っている.したがって,視聴者が私的に利用する以外は,放送内容を録音・録画する場合には,放送事業者の許諾を得る必要がある.著作隣接権の場合,その保護期限は,実演家の演奏,レコードの固定,放送日の翌年から50年間である.
インターネットの普及は,これまでの著作隣接権では対応できない状況を引き起こした.著作隣接権は,放送および有線放送事業者だけを対象にしているため,例えば,インターネットを通じて音楽を配信したり映像を放映したり,さらに受信者がその音楽や映像を録音・録画することに対して,著作隣接権が適用できない状況であった.そこで,著作権法の改正が行われ,実演家やレコード製作者は,インターネットを通じて送信することを可能にする権利(送信可能化権)を有するようになり,録音された実演家の演奏を第三者がインターネットを通じて公衆に配信する場合,著作隣接者の許諾が必要になった.
1.5.5 その他の知的所有権
(1) 商標
商標は,他の商品と区別するために,企業が生産する商品に付けられた標章(マーク)である.また,サービスマークは製品ではなく,企業が行うサービスに対して付けられたマークである.この商標やサービスマークは創造的なデザインであり,売り上げに影響を与えるので,知的所有権に含まれている.この商標は,特許庁に登録することによって保護されており,同一あるいは類似した商標を使用することは禁止されている.
(2) キャラクタ
キャラクタは,漫画やアニメに登場する主人公などの人物や動物の容姿や名称を指す.キャラクタをさまざまな商品に印刷して,キャラクタのイメージを付加して商品価値を高めたり,キャラクタ自体をマスコットなどにして製品化し,販売を促進する手段にしている.このキャラクタは,商品販売やサービス提供の象徴として販売に関与しているため,商品化権とも呼ばれているが,知的所有権として具体的に設定されているわけではなく,著作権法を適用して保護している.
<「サザエさん」事件>
漫画「サザエさん」に登場するキャラクタを,観光バスに大きく描いて営業していたことが問題となり裁判になった.バスに描かれていたキャラクタは,「サザエさん」の漫画の1シーンを複製したものではなかったが,「サザエさん」のキャラクタを無断で利用したと判断され,著作権の侵害と判断された. (3) 肖像権
肖像権は,当事者に無断で個人の姿を撮影したり,氏名の使用を行うことを禁ずる権利である.また,無断で個人の肖像を写真に収め,描写し,あるいは彫刻した作品を公開することは,個人の人格を無視する行為であり,プライバシー保護の観点からも許されるものではない.他者の肖像や氏名を利用する場合には,本人の許諾が必要である.
一方,タレントや俳優などのいわゆる有名人の肖像や氏名を使用して,商品の宣伝に利用することが考えられるが,このような有名人の肖像や氏名の使用に関して,使用料の支払いを要求する財産的権利をパブリシティー権と呼んでいる.